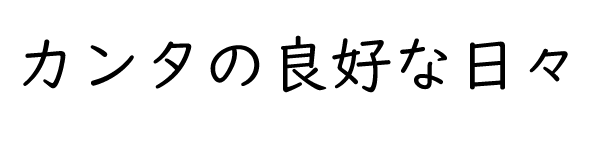皆さんは「法科大学院(ロースクール)」についてご存じだろうか。
法曹界の需要増加を見込み、人材確保のためにそれまでの司法試験の制度を改革し、2004年からスタートした制度である。この制度により、基本的には、法科大学院を卒業しないと弁護士になれなくなった。
旧司法試験と新司法試験で混乱も
法科大学院がスタートした当初は、それまでの司法試験(旧司法試験)と、法科大学院を卒業して受験できる司法試験(新司法試験)が、しばらくの間(移行期間)併存する形となり、当時の司法試験受験生に混乱が生じることにもなった。
ただ、新司法試験の合格率が高くなるという触れ込みもあったため、高い授業料と数年間という時間を犠牲にして、法科大学院へ進む弁護士志願者も多かった。
しかし、当初の予想に反し、法曹界の需要は伸び悩み、弁護士の需要も高まらず、結局司法試験の合格率も大して上がらなかった。
当初の触れ込みでは、法科大学院修了者の司法試験合格率を7割から8割程度と見込んでいたが、最近は2割台に落ち込んでいたという。
また、司法試験に合格したとしても、仕事が無いために、普通の会社の新卒程度かそれ以下の給料に甘んじざるを得ない新米弁護士も続出した。
新司法試験における「三振」
合格率が高くならないことに加え、法科大学院を修了したとしても、新司法試験を受験できるチャンスは3回までと決められていた。
そのため、せっかく法科大学院を修了したとしても、3回の受験資格で合格できず(「三振」と呼ばれる)、費用と時間を無駄にしてしまう人も出てきた。
現在では、チャンスは実質的に5回までに増えたり、予備試験制度などもできたため、若干の規制緩和となっているが、法曹界への道は依然狭き門となっているようだ。
また、予備試験制度自体が、法科大学院の存在意義の低下に繋がっているという指摘もある。予備試験に合格すれば、法科大学院を修了する必要が無いためである。
法科大学院の数が激減
法科大学院は、ピーク時には、74校あったが、来春(2018年度)にむけて募集を続けるのは39校に止まったという。半数近くが廃止もしくは募集停止という事態だ。
青山学院大学、立教大学、桐蔭横浜大学は、今年5月に、法科大学院の学生募集を2018年度から停止すると決定したため、この3校を含めてこれまでに15校が廃止となり、20校が募集停止もしくは停止予定となるという。
この背景には、2015年度から、文部科学省が司法試験の合格率などを基に、大学院への補助金をゼロにする制度を導入したことが大きいようだ。同年度に、一気に13校が募集を停止したという。
政府としては、経済のグローバル化や知的財産分野における弁護士需要の拡大を見込み、それまでは年間1200人程度だった司法試験合格者を3000人にする目標を掲げた。そのために、2016年度までに964億円を支援したという。
しかし、政府の思惑は外れ、法曹界の需要は伸び悩む。
2015年に裁判所が受理した事件数は、約353万件で、2004年よりも約4割減ったようだ。
カンタはこう思う
そもそも、法曹界はそれなりに優秀な人材を必要とするものであり、現状を無視して合格者の数を設定するということには無理があったようだ。そして、政府の需要観測が外れたために、悲惨な状態となってしまった。
日本は、弁護士が管轄する(できる)業務範囲内でも、分野によって「弁理士」や「行政書士」、「司法書士」といってスペシャリストが混在するような状況となっている。そういった「士業」との競争も弁護士需要の低迷に繋がっているのではないだろうか。
そして、弁護士がそれらスペシャリストよりも上位に位置付けられているとしても、例えば知的財産分野で仕事をしたい人は、わざわざ弁護士というハードルが高い資格に挑戦するよりも、弁理士を選択するだろう。
そういった日本独特の構造も、弁護士需要の低迷に関係しているような気がする。
⇒「法律」トップへ