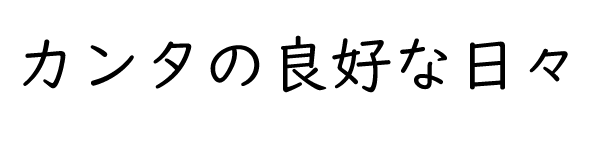2017年7月12日付の科学雑誌『ネイチャー』に、動画データを細菌のDNAに保存し読み出すことに成功したとの論文が発表された。
論文を発表したのは、アメリカのハーバード大学のグループ。
論文によると、生物の遺伝情報を自在に書き換えられる「ゲノム編集」の技術を使って、生きている細菌のDNAに動画のデジタルデータを保存し、読み出すことに成功したという。
デジタルデータとDNAの塩基配列に注目
デジタルデータは、0と1の情報を組み合わせて構成されている。
ハーバード大学は、生物のDNAがA, T, G, Cという4種類の塩基が並べられて構成されていることに注目し、デジタルデータの0と1をA, T, G, Cの塩基に置き換えるルールを作った。
そして、デジタル写真や動画の各画素の色合いを4種類の塩基に置き換えた配列を人工的に作り、それをゲノム編集の技術を使って生きている大腸菌のDNAに組み込んだようだ。
そして、その配列を組み込んだ大腸菌のDNAからデータを読み込んだところ、90%以上の正確さで写真や動画が再現できたという。
菌は寿命が来ると死んでしまうが、分裂して生まれた子供や孫にはDNAが受け継がれる。この性質を利用すれば、組み込まれたデータを後世に残すことも可能だという。
カンタはこう思う
データを保存する場合、データ自体は永久的に保存できるが、データを記録する記録媒体やメディアの寿命が問題である。
一般的な光ディスクの寿命は、数十年から100年くらいと見られているようだ。物質にデータを保存するという方法を採っている限り、物質の経年劣化によるデータの損失というリスクを抱えることになる。
今回発表された技術を使えば、DNAが受け継がれる限り、もしかしたら半永久的にデータを残せるようになるかもしれない。貴重な画像や映像のデジタルデータを数百年・数千年後の未来に残せるようになるかもしれないのだ。
将来は、DNAが記録媒体で使われることになるのかもしれない。生き物が記録媒体で使われるということで、ちょっと怖い感じもするが。
「時事・ニュース」一覧へ