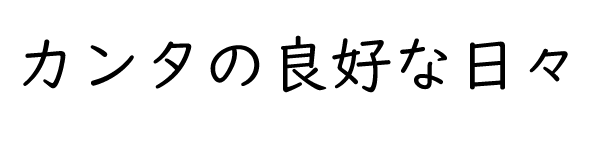夜空を見上げると、様々な星が光って見えます。
実は、星の中には、自らが光り輝くことができる星と、こういった星が発した光を反射する星とがあるのを知っていましたか。
自ら光り輝く星のことを「恒星(こうせい)」と呼びます。
夜空で光り輝いて見える星は、そのほとんどが恒星であるといわれています。
そんな恒星について解説します。
太陽は恒星
恒星は、太陽のように、自らが光を放つ高温のガスでできた球です。
表面は数千度以上!というので、想像も絶する高温ですね。
恒星の中でも、太陽は、我々に最も身近なものだといえるでしょう。
太陽は、自らの原子エネルギーにより、光り輝き、そして高温となっているのです。
間違っても触らないように気を付けなければいけませんね。もっとも、触れることができるほどの距離まで近づくことができれば、の話ですが…。
「恒星」を英語で何という?名前の由来は「固定された星」
恒星の名前の由来は、英語の fixed star を訳したものだとされています。
恒星の「恒」という字には、「変わらない」という意味がありますので、これが英語の fixed(固定された)に当てられたと考えられます。
「恒」の文字や「fixed」の語が示すように、恒星同士は、お互いの位置関係を変えません。
オリオン座などの星座は、恒星によって構成されます(ダジャレではありません)。
そして、恒星がお互いの位置関係を変えないから、私たちは星座を描くことができるわけですね。
恒星の数は?
肉眼で見える恒星の数は限られており、5000個程度であるようです、銀河には、1000億個もの恒星が存在するというから驚きです。
肉眼で見える5000個でもかなり大きな数ですが、1000億個となると気が遠くなるような数ですね。
惑星とは何?
「惑星」とは、恒星の周りを回っている星のことです。
惑星も光って見えますが、これは恒星が放つ光を反射しているために光っているように見えるだけです。惑星は恒星よりも温度が低く、自らが光り輝くわけではないんですね。
地球は惑星
惑星の例としては、我々が住む地球を真っ先に挙げねばならないだろう。
太陽を中心とした太陽系においては、地球は第3惑星とされている。最も太陽に近い惑星である水星が第1惑星だ。
「惑星」を英語で何という?の名前の由来
「惑星」は英語で planet と言うが、これは古代ギリシャで惑星のことを「プラネテス・アステレス(さまよう星)」もしくは「プラネタイ(さまよう者)」と呼んでいたことに由来する。
惑星の「惑」には、「惑う」という意味があり、これが planet に当てられたようだ。惑星は、つまり「惑う星」の意味である。
月の土地を買うことができる?
実は、月の土地を買うことができるのを知っていますか?
興味のある方は、是非ご覧ください。
あなたも月のオーナーになろう!
⇒「 宇宙論・天文学事典 」へ
参考資料:
・二間瀬敏史著、『宇宙用語図鑑』、マガジンハウス、2017年11月9日