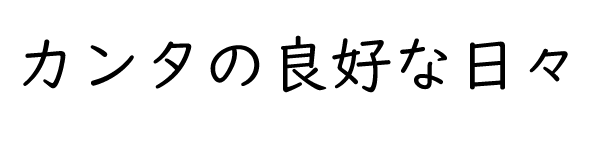世間には様々な情報が溢れている。
しかし、私たちは身近なことさえ知らないことが多い。
例えば、我々が聞いている「音」。この「音」を人間がどのようにして知覚しているのか知っている人は少ない。
今回は、音が聞こえるメカニズムを紹介しよう。
音波が鼓膜を振動
音は、多くの人が知っているように、空気(時には水)の振動で伝わる。これは音波と呼ばれるものだ。
それでは、その音波の振動を「音」として我々が知覚するまでに、どのような順序を経ているのだろうか。
まず、空気などを伝わってやってきた音波は、我々の耳に到達すると、外耳道を通って、鼓膜にぶつかる。
これにより、鼓膜が振動する。
ちなみに、鼓膜は日本語で「鼓の膜」と書くが、英語では eardrum という。文字通りに解釈すれば「耳の太鼓」だ。
このあたりまでは割と常識だと思うので、知っている人がほとんどだろう。
でも、鼓膜が振動したからといって、それがそのまま音として知覚されるわけではない。なぜなら、鼓膜が脳と直接、音の情報をやり取りするわけではないからだ。
鼓膜から脳に音の情報が届くまで
鼓膜には、「耳小骨(ossicles)」と呼ばれる3つの小さな骨がつながっている。これら3つの骨は、ツチ骨(槌骨、malleus)、キヌタ骨(砧骨、incus)、アブミ骨(鐙骨、stapes)だ。
なんかおかしな名前だけれど、これらは全て骨の形がその名前の物の形に似ているから、そう名付けられた。
すなわち、ツチ骨は「槌」つまり木槌とか金鎚などハンマーの形、キヌタ骨は「砧(きぬた)」という布を棒や槌でたたいて柔らかくする台の形、そしてアブミ骨は「鐙(あぶみ)」つまり馬に乗るときに足をかける馬具の形に似ているのだ。英語も、それぞれ同じ意味のラテン語からきている(というか、それを日本語に訳したと考える方が自然)。
鼓膜の振動は、ツチ骨、キヌタ骨、そしてアブミ骨の順に伝わり、アブミ骨から今度は「蝸牛(かぎゅう)」と呼ばれる内耳器官に伝わる。
「蝸牛」というのは、今でいうカタツムリのこと。カタツムリのように巻貝のような形をしているからそう名付けられた。
この蝸牛には、リンパ液が入っている。そして、蝸牛に振動が伝わると、内部にあるリンパ液が揺らされるのだ。
リンパ液が揺らされた際の圧力波を蝸牛の有毛細胞が感じ取って、化学信号に変換して、聴神経に伝える。
そして、聴神経はこの信号を電気インパルスに変換して、脳に伝える。
こうして、我々は音を認識することができる、というわけだ。
こうしてみると、音波を我々が「音」として感知するまで、複雑なメカニズムが働いているのが分かる。