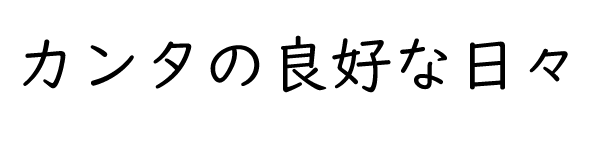「プラセボ」、もしくは「プラシーボ」とは、英語で placebo と書き、日本語ではしばしば「偽薬」とも表記される。
プラセボには、一般的にブドウ糖や生理的食塩水などを用いる。それ自体には、何の効果も持たないとされる。
しかし、プラセボ(偽薬)自体には何の効能もないのに、本当の薬と同等、もしくはそれ以上の効果を示すことがある。これを「プラセボ効果」(もしくは、「プラシーボ効果」、「偽薬効果」)と呼ぶ。
なぜプラセボ効果が起こるのか
プラセボ効果の発生には、「エンドルフィン(endorphin)」が関与している場合があると考えられている。
エンドルフィンとは、脳内で作り出される化学物質で、「天然の鎮痛剤」のような働きがある。
プラセボを投与された患者が、本物の薬を投与されたと思い込むことにより、脳内でエンドルフィンが作り出されるのである。
これにより、あたかも鎮痛剤を投与されたかのような効果が表れるのである。
神経科学者のジョン・レビンは、口腔外科手術を受けた患者にプラセボを投与し、痛みが引いたとの報告を受けた後、エンドルフィンの効果を阻害する薬を投与した。すると、痛みがぶり返したという。
これにより、プラセボによってエンドルフィンが作り出されることが分かった。
もちろん、プラセボ効果は人間の心理によって発生するため、患者が「薬を投与された」ことを知らなければならない。
また、プラセボ効果が現れるのは、特定の症状に限られる。
プラセボ効果の例
・背骨にヒビが入り、痛みのために通常の生活を送れなくなった年配の女性に、手術を行ったところ、痛みが引き、趣味のゴルフを再開するまでに回復した。しかし、手術は偽の手術であった。
このように、プラセボ効果は、薬の投与のみならず、質の高い治療を行ったという思い込みだけでも発生することがある。
・パーキンソン病患者にプラセボを投与したところ、脳内に本物の治療薬を投与したときと同等のドーパミン濃度が見受けられた。一般的に、パーキンソン病の治療としては、脳内のドーパミン濃度を高める薬が投与される。
・重症患者の除く大半の症例で、プロザックなどの抗うつ剤には、プラセボを超える効果がほとんどなかった、という。